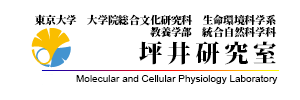トピックス
肝臓の概日リズムの乱れは過食を引き起こす日光や食事によって調節される24時間周期の生体リズムを、概日リズムといいます。概日リズムは、全身の細胞に存在しており、脳の深部にある視交叉上核が、それらを統合し、管理しています。これまでの研究により、夜勤や時差によって、肝臓と脳が刻む概日リズムにズレが生じると、肥満や代謝異常の原因となることが分かっていました。しかし、肝臓における概日リズムのズレが、どのようにして脳へと伝わるのかは、詳しくわかっていませんでした。
そのメカニズムを明らかにするために、ペンシルベニア大学のある研究チームは、肝臓における「時計遺伝子」の機能を欠損させることで、肝臓の概日リズムだけが乱れたマウスを作出し、いくつかの実験を行いました。
その結果、そのマウスでは、肝臓の概日リズムが乱れているだけにもかかわらず、食欲を司る脳領域の遺伝子発現が変化し、日中の摂食量が約2倍に増加することが分かりました。マウスは夜行性であるため、このことは、私達が夜中に大食いをしてしまう状態に当たります。さらに、血中の成分解析することで、このような摂食パターンの変化は、ホルモンなどの血中の物質によって引き起こされているわけではないことが分かりました。
そこで研究チームらは、内臓と脳との神経伝達経路である、求心性迷走神経に注目しまし、肝臓の概日リズムが乱れたマウスに、求心性迷走神経を切断する手術を施しました。その結果、求心性迷走神経を切断すると、マウスの日中の摂食量が正常に戻ることが分かりました。つまり、肝臓の概日リズムのズレは、求心性迷走神経を介して脳へと伝わり、摂食パターンの変化を引き起こしていたのです。この研究成果をもとに、肥満や代謝異常の新たな予防法や治療薬の開発が期待されます。
紹介論文: Hepatic vagal afferents convey clock-dependent signals to regulate circadian food intake. Science. 7 Nov 2024. Vol 386, Issue 6722pp. 673-677.