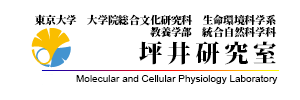トピックス
脂肪が腸を狭くする ~クローン病における腸の狭窄と脂肪の繋がり~消化管全体で断続的な炎症を生じるクローン病(Crohn's disease: CD)は、潰瘍性大腸炎(Ulcerative colitis: UC)とともに炎症性腸疾患に分類されます。原因不明の腸疾患であり、日本ではUCとともに国の難病に指定されています(登録番号96)。
CDでは、消化管の筋肉の層が肥厚することで管腔が狭くなる「狭窄」が起こることが知られています。狭窄は腸管の生理機能を阻害するのみならず、腸閉塞を始めとした他の腸疾患を併発するリスクを高めるため、炎症と並んで治療すべきCDの表現型と言えます。
CDのもう一つの特徴として、脂肪組織が腸管を囲むように発達するCreeping fatがあります。先行研究では、このCreeping fatが腸管の狭窄に寄与することが示唆されてきました。しかしcreeping fatが腸管の狭窄、特に筋層の肥厚にいかにして寄与するかは不明でした。
筆者らは、まずヒト小腸の組織サンプルにおいて、腸管の筋層の分厚さと脂肪組織の有無との関連を調べました。するとCD患者の小腸では、Creeping fatと接触した部分において筋層が肥厚していることが分かりました。また、後天的に脂肪組織の発達を阻害したマウスで腸炎発症モデルを作製し、筋層の状態を調べました。すると、通常のマウスで腸炎モデルを作るとCreeping fatと接した筋層が肥厚する一方、脂肪組織の発達を阻害しCreeping fatが生じないマウスでは、炎症が起きても筋層の肥厚が見られませんでした。以上の結果から、Creeping fatが筋層の肥厚に実際に寄与していることが示唆されました。
続いて、ヒトのCreeping fatおよび通常の脂肪組織サンプルをマススペクトロメトリーによって解析しました。その結果、Creeping fatからは遊離長鎖脂肪酸(free fatty acid, FFA)が盛んに放出されていることが分かりました。次に、ヒトの小腸から採取した筋細胞を培養し長鎖脂肪酸を投与したところ、特にパルミチン酸を投与した際に細胞の増殖が亢進しました。このことから、Creeping fatが放出する長鎖脂肪酸、とりわけパルミチン酸およびその代謝産物が筋細胞の増殖を促進し、筋層の肥厚に寄与している可能性が示唆されました。
並行して行っていた次世代RNAシーケンスでは、CD患者の筋細胞においてミトコンドリア関連の遺伝子発現が大きく変化していました。そこで、小腸筋細胞へのパルミチン酸投与を行う際に、パルミチン酸代謝およびミトコンドリアによる脂質取り込みの阻害を並行しました。その結果、classic Kennedy pathwayと呼ばれる経路の代謝産物(Palmitoyl-CoA)のミトコンドリアへの取り込みが、筋細胞の増殖に重要であることが示唆されました。
最後に、腸炎モデルマウスに対してミトコンドリアによる脂質取り込みの阻害剤を継続的に投与しました。その結果、腸炎モデルマウスにおける筋層の発達が抑制され、ミトコンドリアへの脂質移行が筋細胞の増殖に重要であることが個体レベルで認められました。
炎症という最も特徴的な症状との関連は依然として不明であるものの、CDにおいて腸管の狭窄が起こる仕組みにCreeping fatという視点から新たに光を当てた研究と言えます。 紹介論文: Creeping Fat–Derived Free Fatty Acids Induce Hyperplasia of Intestinal Muscularis Propria Muscle Cells: A Novel Link Between Fat and Intestinal Stricture Formation in Crohn’s Disease.Gastroenterology, 168, 508-524, 2025.