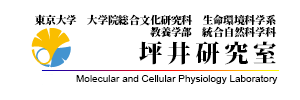トピックス
腸内細菌叢の変化が引き起こす肝炎代謝機能障害関連脂肪肝炎(metabolic dysfunction-associated steatohepatitis: MASH)は、アルコールを全くあるいはほとんど摂取しないにもかかわらず、肝臓への脂肪の蓄積、次いで線維化や炎症を呈する疾患です。以前はNASH(nonalcoholic steatohepatitis)と呼ばれていましたが、一昨年のガイドライン改定に伴いMASHと改称されました。
筆者らの研究グループは以前、腸管バリアの破綻や腸内細菌叢の組成の変化がMASHの発症に寄与することを報告していましたが、その分子メカニズムは不明でした。
それとは別にMASH発症に関わる因子として従来報告されていたのが、Transmembrane-6 superfamily member 2(TM6SF2)でした。TM6SF2は肝臓における脂質の代謝に重要な因子ですが、肝臓よりも小腸に多く発現することが知られています。筆者らは小腸のTM6SF2が腸内細菌を介したMASH発症機構に関与するのではないかという仮説の下、TM6SF2を腸管上皮細胞特異的にノックアウトしたマウス(以下、KOマウス)を作製し、MASH症状と腸内細菌叢・腸管バリア機能の変化との相関を検証しました。
KOマウスの肝臓組織を観察すると、通常の食事を与えた場合と高脂肪食を与えた場合の両方において、脂肪の蓄積と炎症という主要なMASH症状が認められました。
次にKOマウスの小腸に注目し、腸管上皮の形態と腸内細菌の組成を観察ました。電子顕微鏡を用いた観察により、腸管上皮叢の細胞同士を接着するtight junctionが弛緩し、細胞の間隙が広がってバリア機能が破綻していることが認められました。また特定の腸内細菌が増加あるいは減少しており、細菌叢の組成の変化が見られました。
続いて、これらの減少とMASHの病態とを仲立ちする分子の実態を調べるため、腸内細菌代謝物の解析を行いました。糞便、肝門脈血、肝組織の各サンプルを調べたところ、KOマウスにおいてリゾホスファチジン酸(LPA)が有意に増加していました。また、KOマウスにおいて増加していた細菌を非KOマウスに与えると、各組織でLPAが上昇しました。
さらにKOマウスの小腸上皮を単離・培養し分泌された物質を調べると、各種遊離脂肪酸が増加していました。それらはLPAやKOマウスで優占的な細菌量と相関しており、小腸上皮が遊離脂肪酸の過剰な分泌を介して一連の病態を形成する可能性が示唆されました。
その後の実験で、無菌マウスに対するKOマウスの糞便移植によってMASH症状を呈すること、非KOマウスとの同居による細菌叢の調節でKOマウスの症状が緩和されることを認めました。最後にLPA受容体(肝臓に発現することが知られています)の阻害剤をKOマウスに腹腔投与することで、MASH症状の抑制を認めました。
腸管と肝臓の生理機能が相互に連関する腸-肝(あるいは肝-腸)軸は、近年注目を集めている研究課題です。異なる組織・器官の相互作用から、疾患の新たな治療標的を分子レベルで提唱した点で、大きな意味を持つ研究と考えられます。
紹介論文: Intestinal TM6SF2 protects against metabolic dysfunction-associated steatohepatitis through the gut–liver axis Nature Metabolism 7, 102-119, 2025