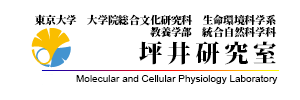トピックス
タコと魚の狩猟グループにおける狩りのしかた動物の集団行動、個体間の相互作用、そしてリーダーシップはグループに属するメンバーの個体差によって左右されます。しかし、ほとんどの研究では、一種のみで構成された個体差が少ないグループが扱われてきました。そこで研究チームは、無脊椎動物であるタコと脊椎動物である魚類の狩猟チームに着目し、多様性溢れるグループにおけるリーダシップについて検証しました。
研究チームは広角カメラを駆使して長時間の水中撮影を行い、狩猟グループの各個体が移動した軌跡を3次元で記録しました。そして個体同士の動きを、2種類に分類しました。2個体のうち1個体が離れたとき、もう片方の個体も移動に追随した場合は、相手を「引っ張った」とし、離れた個体がもう片方の個体の元に戻ってきた場合は相手に位置を「固定」されたと定義しました。つまり「引っ張り」は移動を促進し、「固定」は抑制します。
上記の基準に基づいて、個体間の動きを検証したところ、アオヒメジ(魚の一種)は動きを開始する頻度と「引っ張り」の頻度が多く、集団行動の駆動力となっていました。アオヒメジはグループを動かすことで、環境の探索を促進し、獲物を見つける機会を増やします。アカハタ(魚の一種)は、「引っ張り」と「固定」の効率が高く、グループへの影響力が大きいことが分かりました。アカハタは待ち伏せして獲物を捕食するため、アカハタの移動の有無がその場に獲物がいるかどうかの指標となっている可能性があります。タコはグループの中で最も「固定」の頻度が高く、グループの移動のタイミングを決定していました。さらに、タコは怠けている魚を攻撃(パンチ)して、働かせていました。
以上のことから、タコと魚類で構成された狩猟グループは、1個体が独裁的にリーダーシップを取るのではなく、多次元に跨った個体間の相互作用を介して、メンバー全員でグループの方針を決めていることがわかりました。
紹介論文: Multidimensional social influence drives leadership and composition-dependent success in octopus–fish hunting groups. Nature Ecology & Evolution (2024)